上がる結婚年齢と不妊治療の関係国内の治療件数と年齢別の成功率

2020年の生殖補助医療実施数は449,900件で、生殖補助医療によって生まれた赤ちゃんは60,381人でした。
これまでに体外受精で生まれた赤ちゃんは約710,931人となりました。
加齢と妊娠に至る確率
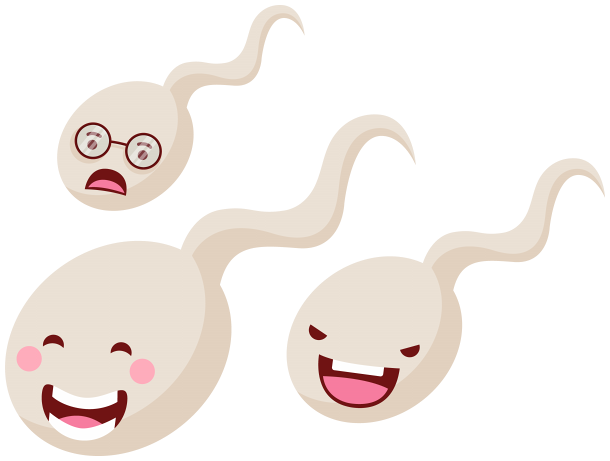
年齢が上がるにつれ、妊娠に至る確率は減ることが医学的に分かっています。
さらに体外受精をはじめとする不妊治療の成功率も年齢とともに下がってしまいます。
前述の調査では、年齢別の生殖補助医療による出生率は、30歳女性で32.6%、35歳27.9%、40歳14.0%、45歳では1.6%と、年齢を重ねるにつれて右肩下がりとなっています。
また、男性についても、加齢とともに精液の量や精子濃度、総運動精子数、正常形態精子が減少し、妊娠率が低下することがわかっています。
不妊治療についてパートナーと良く話し合いましょう

不妊治療には、手術や薬、生殖補助医療などの選択肢がありますが、必ずしもすべての人が妊娠できるわけではありません。
また、不妊治療が長期間にわたると、身体的・精神的な負担だけでなく経済的な負担も大きくなります。
この負担を軽減するため、2022年4月から不妊治療の保険適応が拡大しております。
治療法や対象者、年齢・回数制限などもあり、不妊治療についてパートナーとよく考える必要があります。
POINT
- 年齢が上がるにつれ、妊娠に至る確率は減り、さらに不妊治療の成功率も下がってしまいます。
- 2022年4月から不妊治療の保険適応が拡大しておりますが、治療法や対象者、年齢・回数制限などもあり、不妊治療についてパートナーとよく考える必要があります。
- どこまで不妊治療を受けるのかを、パートナーと考える必要があります。


